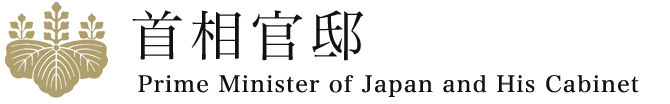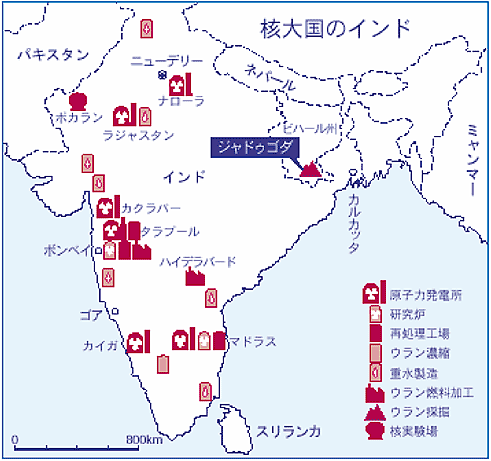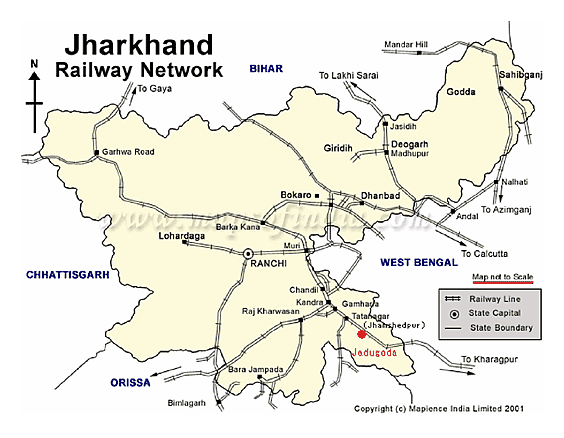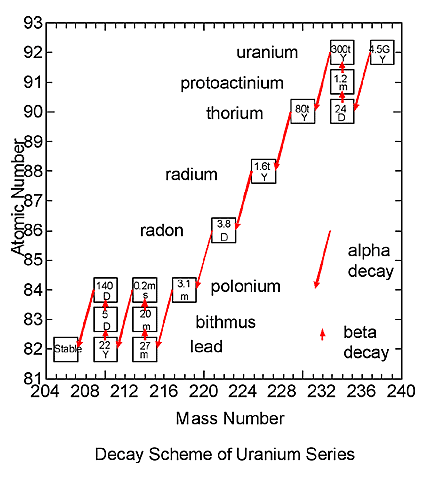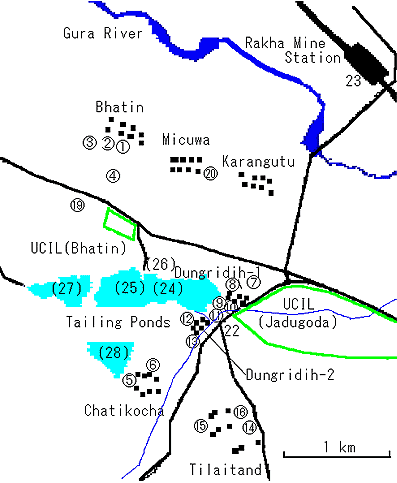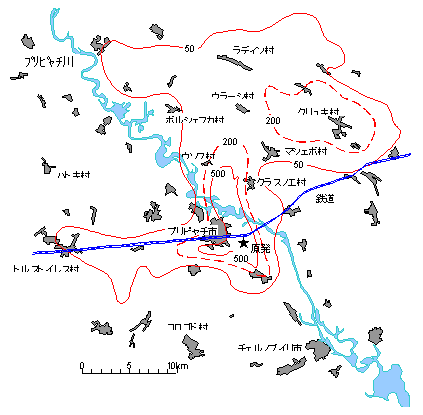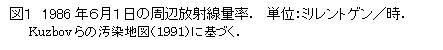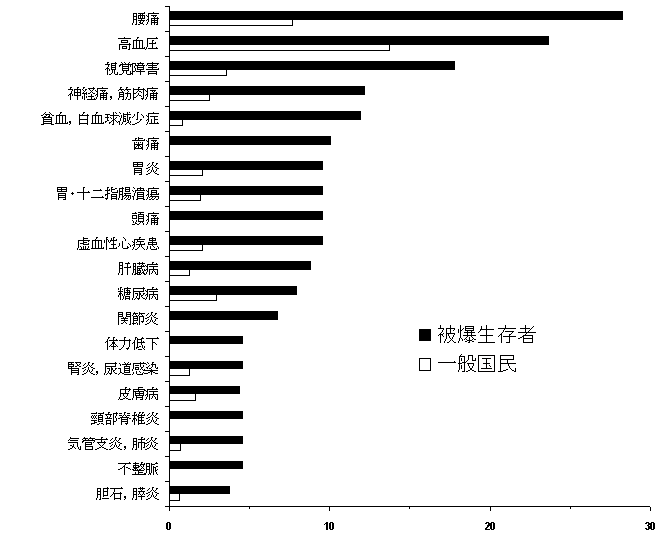(1)
ミハイル・V・マリコ
ベラルーシ科学アカデミー・物理化学放射線問題研究所
はじめに
チェルノブイリ事故から11年たった(1997).この間,多くのデータが ベラルーシ,ロシア,
ウクライナの科学者によって明らかにされてきた. これらのデータは,チェルノブイリ事故
が原子力平和利用における最悪の事故であったことを はっきりと示している.
この事故は ベラルーシ,ロシア,ウクライナの環境に 大変厳しい被害を与え,これらの国
の経済状態を決定的に悪化させ,被災地の社会を破壊し,汚染地域住民に不安
と怖れをもたらした.そして,被災地住民 と その他の人々に 著しい生物医学的な
傷を与えた.
今日,チェルノブイリ原発の核爆発が生態学的,経済的,社会的 そして心理学的に,
どのような影響を及ぼしたかについては 議論の余地がない.
一方, この事故が 人々の健康に どのような放射線影響を及ぼしたかについては,著しい評価の食い違いが存在している.
チェルノブイリ事故直後に,被災した旧ソ連各共和国の科学者たちは,多くの身体的な
病気の発生率が著しく増加していることを確認した.しかし,“国際原子力共同体”
は,そのような影響は 全くなかったと否定し,身体的な病気全般にわたる発生率
の増加 と チェルノブイリ事故との因果関係を否定した.
そして,この増加を,純粋に 心理学的な要因やストレスによって説明しようとした.
“国際原子力共同体”が こうした立場に立った理由には,いくつかの政治的な
理由がある.また,従来,放射線の晩発的影響として認められていたのは,白血病
,固形ガン,先天性障害,遺伝的影響だけだったこともある.
同時に,“国際原子力共同体”自身が 医学的な影響を認めた場合でも,例えば
彼らは チェルノブイリ事故によって引き起こされた甲状腺ガンや先天性障害の発生を
正しく評価できなかった.
同様に,彼らには,チェルノブイリで起きたことの 本当の理由も 的確に理解することが
できなかった.
こうしたことを見れば,“国際原子力共同体”が危機に直面していることが分かる.
彼らは,チェルノブイリ事故の深刻さ と放射線影響を評価できなかったのであった.
彼らは旧ソ連の被災者たちを救うために客観的な立場をとるのでなく,事故直後から 影響を過小評価しようとしてきたソ連政府の代弁者の役を演じた.
本報告では,こうした問題を取り上げて論じる.
チェルノブイリ事故原因と影響についての公的な説明
チェルノブイリ原発事故は,原子力平和利用史上最悪の事故として 専門家に知られ
ている.事故は 1986年4月26日に発生した. その時,チェルノブイリ原発4号炉の
運転員は,発電所が 全所停電したときに,タービンの発電機を使って短時間だけ
電力を供給するテストを行なっていた.
事故によって 原子炉は完全に破壊され,大量の放射能が環境に放出された.
当初,ソ連当局は 事故そのものを隠蔽してしまおうとしたが,それが不可能だった
ため,次には 事故の放射線影響を小さく見せるように動いた.
事故後すぐに,国際原子力機関(IAEA) と ソ連は 事故検討専門家会議を ウィーン
で開くことに合意し,その会議は 1986年8月25日から29日に開かれた.その会議
で,ソ連の科学者は 事故と その放射線影響について偽りの情報を提出した.
ソ連当局の見解では,事故の主な原因は,チェルノブイリ原発の運転員が運転手順書
に違反したためだとされた.ソ連の専門家は また,チェルノブイリ事故による放射線影響
の予測も示した.その評価によれば,確定的影響 (訳注:急性の放射線障害など一定
のレベル以上の被曝で生じる障害) を被るのは,事故沈静化のために働いた原発職員
と消防隊だけであるとされた.
彼らは,住民には 確定的影響が現れる可能性はないとし,また 確率的影響(訳注:
ガンや遺伝的影響など,確率的に発生する晩発性障害) も 無視できる程度でしかない
という予測を示した.例えば,線量・効果関係に 閾値がないとした仮定に基づいて
評価しても,ガンの死亡率の増加は 自然発生ガン死に比べて,0.05%以下にしか
ならない というのが彼らの予測であった.
この結果は,ソ連のヨーロッパ地域(約7500万人)の人々についての計算であった.
ソ連からの説明は 会議参加者によって 完全に受け入れられた.そのことは,
1986年9月に IAEAが発行した事故検討専門家会議の要約報告を読めば分かる.
その報告の28ページには,以下のように書かれている.
「 前述の説明は,ソ連の専門家が提出した作業報告や情報に基づいている.
この情報に基づく チェルノブイリ4号炉事故の経過は もっともなものとして理解できる.
そのため,別の説明を求めるための試みは行なわなかった. 」
同じ報告の17ページには以下のようにある.
「 誤操作 と 規則違反が,事故を引き起こした主要な要因である. 」
IAEAの会議に出席した人たちは,ソ連の専門家が示した放射線影響の予測に
ついても同意した.そのことは,IAEAの事故検討専門家会議の要約書7ページに
以下のように書かれていることから分かる.
「13万5000人の避難者の中に,今後70年間に増加するガンは,自然発生のもの
に比べて,最大でも 0.6%しかないであろう.同じように,ソ連のヨーロッパ地域の
人口についていうならば,この値は 0.15%を超えないものとなるし,恐らくは
もっと低く,0.03%程度の増加にしかならないであろう.甲状腺ガンによる死亡率
の増加は 1%程度になるかもしれない. 」
国際原子力共同体の,こうしたものの見方は,今日に至るまで変っていない.
事故検討専門家会議が,チェルノブイリ事故原因と放射線影響について もっともらしい
説明をし,それが 国際原子力共同体によって受け入れられてきた.
しかし,これらの説明は誤っており 正しくない.今日では,事故の本当の原因は,
ウィーンでの事故後検討会議で述べられたような運転員の誤操作ではなく,RBMK型
原子炉(訳注:「チャンネル管式大出力原子炉」という ロシア語の略.チェルノブイリ原発では,この型
の原子炉が4基稼働していた)原子炉そのものが持つ欠陥にあることが知られている.
最も重要な欠陥は,
- 大きな正のボイド係数
- 低出力における不安定性
- 出力暴走の可能性
- 不適切な制御棒(制御棒の下端に黒鉛でできた水排除棒がつながれていた)
である.
IAEAが チェルノブイリ事故の本当の原因について 正しい説明にたどり着くまで,
ウィーンでの事故後検討会議から 何と7年もかかったことに注意しておこう.
そこで疑問が起こる. ウィーンの会議で,ソ連の専門家たちは,RBMK型原発の
安全性を向上させるための改善策を練っていることを語った.即ち,燃料濃縮度を
2.0%から 2.4%に引き上げること,炉心に挿入する制御棒の数を増やすこと
である (これら2つの方策は,事故の主要な原因の一つであった RBMK型原発が持つ正の
ボイド係数問題を改善するために導入されたものである). 西側諸国の専門家たちは,
こうしたことを知った後で,なぜ チェルノブイリ事故原因についての 別の説明を探して
みようとしなかったのであろうか? より迅速に作動する炉停止系と,その他の幾つ
かのシステムを採用するという改善策もまた知られていたのである.
ウィーンでの事故検討専門家会議の参加者たちが,どうして 事故の本当の原因を
理解できなかったのか? これについては,2つの解釈の仕方がある.
第1の解釈は,この会議に参加した専門家には,RBMK型原子炉の特性が 本当に
理解できなかったというものである.
第2の解釈は,原子力の イメージを守るために,ソ連の公式見解に疑いをさし挟み
たくなかったというものである.
第1の解釈は およそ信じがたい.なぜなら,ウィーンの事故検討専門家会議でソ連
の専門家が示した,RBMK型原子炉の核的安全性を改善するための方策の全て
が,この型の原子炉の設計に欠陥があることを はっきりと示していたのである.
2番目の解釈の方が より当たっているように思えるし,もし そうだとするならば,
原子力安全の場にいる専門家たちは 原子力平和利用がもつ 真の危険性を隠蔽
するつもりだ ということになり,いっそう 不愉快なものである.
IAEAが 文献3を公表したことにより,チェルノブイリ事故原因についての誤った説明
は実質的に行なわれなくなった.しかしながら,事故による放射線影響については,
いまだに異なった立場が存在している.
実際,今日に至ってもなお,国際原子力共同体は,チェルノブイリ事故の放射線影響
はほぼ無視できると主張している.1995年になって ようやく,彼らはベラルーシ,ロシア
,ウクライナでの甲状腺ガンの多発と放射線被曝との関連を認めた.
しかし,ベラルーシ,ロシア,ウクライナの専門家たちが見いだした その他の全ての影響
については,完璧に否定している.
例えば,ベラルーシの被災地における先天的障害発生についての G・ラジューク教授
たちの データを,国際原子力共同体は認めていない. 同じように,ベラルーシ,ロシア,
ウクライナで 事故直後に確認された,様々な身体的な病気の発生率が はっきりと
増加したという 貴重な統計学的 データについても認めようとしない.
ソ連の専門家は,チェルノブイリ事故の放射線影響は 観察することさえできないもの
だとし,それが ウィーンの事故検討専門家会議で受け入れられた.そして,チェルノブイリ
事故による放射線影響に関するかぎり,国際原子力共同体は 未だに その考え方
を支持し続けている.
こうした国際原子力共同体の立場は,事故直後からチェルノブイリ事故の放射線影響
を過小評価しようとしてきた ソ連当局にとって,大変重要なものである.
事故当時,ソ連は 大変 困難な経済危機に陥っていたため,ベラルーシ,ロシア,ウクライナ
の被災者たちに 必要な援助をすることができなかった.ソ連にできたことは,被災者
に対するごく限られた援助だけであった.そのため,旧ソ連の時代には,チェルノブイリ
事故 と その影響に関する すべての情報は秘密にされた.それも 大衆に対して
だけでなく,多くの場合,放射線防護の専門家に対してさえ 秘密にされたのであった.
例えば,1986年の事故検討専門家会議に提出されたソ連の専門家によるデータは,
ソ連国内では長い間,秘密であった.ソ連国内の汚染地域でとられていた防護処置
についての文書も また秘密にされていた.
チェルノブイリ事故被災者の医学的影響
「350ミリシーベルト概念」
いわゆる 350m㏜概念,すなわち,被災者の被曝限度を 一生の間に 350m㏜と
定めた主な理由は,おそらくソ連の複雑な経済状況であった.この概念は1988年秋
に ソ連放射線防護委員会(NCRP)によって作られた.
この350m㏜概念は,以下の仮定に基づいている.
・ソ連国内汚染地の大多数の住民にとって,外部被曝と内部被曝を合わせた,
チェルノブイリ事故による個人被曝は,1986年4月26日を起点とする70年間に
350m㏜を超えない.
・汚染地域で生活する人の全生涯に,事故によって上乗せされる被曝量が
350m㏜程度かそれ以下であれば,住民への医学的な影響は問題にならない.
こうした仮定により,ベラルーシ,ロシア,ウクライナの全チェルノブイリ被災地において,移住を
含めた 何らの防護措置も実質的に行なう必要がなくなった.
この350m㏜概念は,1990年1月から実施されるはずであった.その実施によって,
事故後汚染地でとられてきた すべての規制は解除されることになっていた.
350m㏜概念は,1986年夏にソ連の専門家が行なった医学影響予測に基づいて
いる.また,1988年末 イリイン教授の監督のもとで行なわれた改訂版の評価にも
基づいている.その新しい評価は,昔のものと 非常によく一致していた.
しかし,古い評価と同様,新しい評価も正しくない.そのことは,甲状腺ガンの評価
から はっきりと見て取れる.新しい評価によれば,チェルノブイリ事故によってベラルーシ
の子供たちに引き起こされる甲状腺ガンは,わずか 39件とされている.そして,
その症例は 5年の潜伏期の後,30年かけて現れるはずであった.
つまり,ベラルーシの子供たちに はじめて甲状腺ガンが増えてくるのは,1991年に
なってのことだ と予測されていた.
イリイン教授らの予測は 完全に誤りであった.そのことは,表1に示すベラルーシに
おける甲状腺ガン発生件数の データをみれば分かる.チェルノブイリ事故前9年間(1977
-1985) においては,ベラルーシで登録された小児甲状腺ガンは わずか7例であった.
つまり,ベラルーシにおける自然発生の小児甲状腺ガンは,1年に 1件だということ
である.ところが,1986年から 1990年の間に,47例の甲状腺ガンが確認され,
それは イリインらによる予測に比べれば 9倍以上に達する.
表1 ベラルーシにおける甲状腺ガン発生数
(大人と子供)
事故前 | 事故後 |
年 | 大人 | 子供 | 年 | 大人 | 子供 |
1977 | 121 | 2 | 1986 | 162 | 2 |
1978 | 97 | 2 | 1987 | 202 | 4 |
1979 | 101 | 0 | 1988 | 207 | 5 |
1980 | 127 | 0 | 1989 | 226 | 7 |
1981 | 132 | 1 | 1990 | 289 | 29 |
1982 | 131 | 1 | 1991 | 340 | 59 |
1983 | 136 | 0 | 1992 | 416 | 66 |
1984 | 139 | 0 | 1993 | 512 | 79 |
1985 | 148 | 1 | 1994 | 553 | 82 |
合計 | 1131 | 7 | 合計 | 2907 | 333 |
チェルノブイリ事故後最初の10年,つまり 1986年から 1995年の間にベラルーシで確認
された甲状腺ガンの総数は,424件であった.この値は,事故後35年の間に 全部
で 39件の小児甲状腺ガンしか生じないという イリインらの予測に比べ,すでに 10倍
を超えている.予測と実際を比べてみれば,チェルノブイリ事故による小児甲状腺ガン
の発生について,ソ連の専門家の予測は 大変 大きな過小評価をしていたことが
分かる.
同じことは,旧ソ連の汚染地域における先天性障害に関してもいえるであろう.
ソ連の専門家の評価は,それが見つかる可能性すら 実際上否定していた.その
結論の誤りが,ラジューク教授らによって示されたのであった.
上述した事実は,チェルノブイリ事故による放射線影響に関して ソ連の専門家が
行なった評価が,著しい過小評価であることを はっきりと示している.そのことは,
ベラルーシ,ロシア,ウクライナの汚染地域において,事故直後から被災者の間に健康状態
の顕著な悪化を確認してきた 多くの科学者たちにとっては,自明のことであった.
ところが,ソ連当局と国際原子力共同体は,彼らの評価結果 と 350m㏜概念が
正しいと考えていた.国際原子力共同体が,チェルノブイリ事故の放射線影響に関する
ソ連の新しい評価 や 350m㏜概念の意味するものを十分に承知していることに
注意しておかねばならない.
ソ連医学アカデミーの会議の後,イリイン教授らの報告は,世界保健機構(WHO)に
提出され,後日 それは,有名な国際雑誌に 科学論文として掲載された.
350m㏜概念についても同様である.その350m㏜概念に関する報告は,1989年
5月11-12日に ウィーンで開かれた国連放射線影響科学委員会の第38回会議において,
イリイン教授によって提出された.
この概念は,国際原子力機関(IAEA)事務局が 1989年5月12日に開いたチェルノブイリ
事故影響に関する非公式会議にも提出された.
このソ連の新しい評価は,国際原子力共同体の専門家からは 何らの批判も受け
なかった.そのことは,イリイン教授らの論文の内容が,もとの報告と大きく変わって
いなかったことからも分かるし,ソ連政府に 350m㏜概念を実施させるために国際
原子力共同体が多大な手助けをしたことからも分かる.
(つづく)